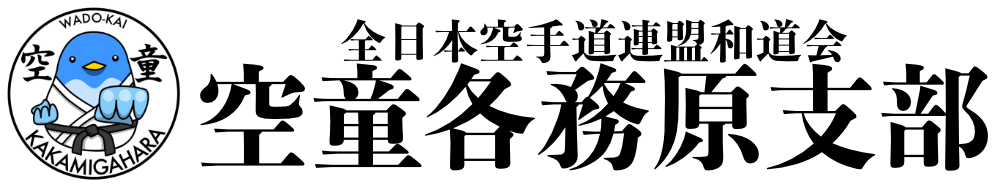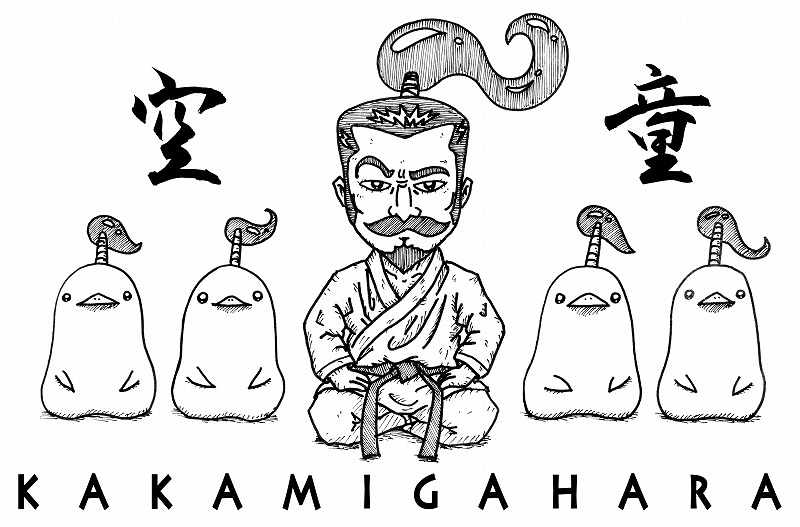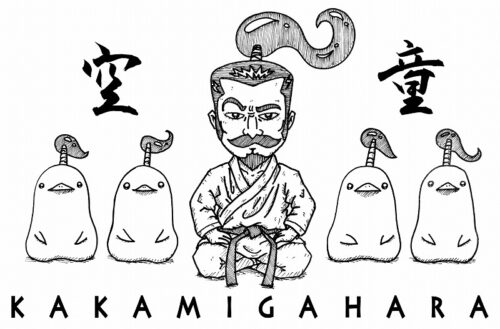そもそも和道流って何?
空手といえば「押忍!」「バシッ!」って感じで力強く攻撃するイメージあると思うんですよね?
でも和道流はちょっと違うんです。
どっちかっていうと「スッ」「サッ」って感じ。
力でゴリ押しするんじゃなくて、相手の力を利用してサラリといなす(往なす)。
要するに、「喧嘩しないで勝つ」のが得意な流派なんです。
で、これを作ったのが大塚博紀(おおつかひろのり)先生!
この先生、ただの空手家じゃくて、実は柔術の達人だったんです!
✳️ 「往なす(いなす)」っていう言葉は、相手の攻撃や勢いをうまく受け流す っていう意味。
和道流誕生秘話 〜空手 × 柔術のハイブリッド〜
大塚先生は若い頃から「柔術」っていう、相手の力を利用して戦う武術を学んでたんです。
これがすごい!
敵の攻撃をいなして、スルッと技をかけてしまう。
でも、時代が変わって柔術が廃れそうになってきた頃、「空手ってのがすごいらしいぞ!」って話を聞くわけです。
そこで大塚先生、沖縄の船越義珍(ふなこしぎちん)先生に弟子入りして空手を学ぶんです。
「これはすごい!」と感動した大塚先生、でもこう思いました。
「空手もいいけど、柔術の技を入れたらもっと面白くなるんじゃないか!?」
そこで、自分の得意な柔術と、学んだ空手を融合させて作ったのが 和道流 なんです!
和道流の特徴 〜まるで武道のカクテル〜
和道流の面白いところは「空手 + 柔術」だから、他の流派とはちょっと違う動きが多い。
1. 相手の攻撃をかわす!
他の流派が「受け止める」「弾く」なら、和道流は「いなす」!相手がパンチしてきたら、ちょっと横に動いてヒョイッと避ける。
これ、まるで武道界の忍者みたいでカッコいい!
2. 関節技もある!
空手といえば「突き」「蹴り」だけかと思いきや、和道流には柔術由来の「関節技」が入っています。
つまり、ガッツリ組んでも戦える、ことになっている。
3. 戦わずして勝つのが理想!
これは大塚先生の教えなんですけど、「本当の武道は、戦わずに済むことが最強の技」っていう考え方。
つまり、戦う前に相手の気を制する ことが大事なんですね。
ちょっと面白いエピソード
和道流って海外でも人気があるんですけど、昔、あるイギリスの選手が「和道流の動きってまるでダンスみたい」って言ったことがあるんです(笑)。
確かに、スムーズで優雅な動きが多いから、空手というより「舞うように戦う」って感じなんですよね。
あと、大塚先生はすごく研究熱心な人で、なんと 90歳 まで現役で空手を教えてたんです!
「武道は一生修行」っていうのを、本当に体現してた人だったんですね。
まとめ
😊 和道流は、空手と柔術のいいとこ取りをした「戦わずして勝つ」武道!
😊 動きはスムーズでしなやか、関節技もあって、まるで武道のカクテルみたいな流派!
😊 力がなくても戦えて、「頭を使って勝つ」っていうのが和道流の面白いところ!
まさに 「戦わないで勝つ」究極の空手 というわけですね!