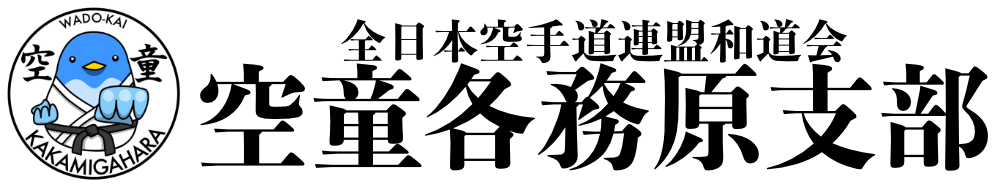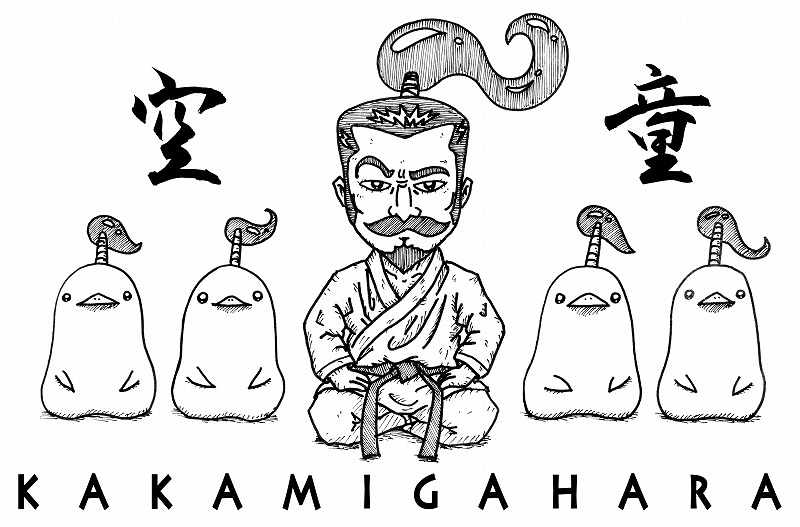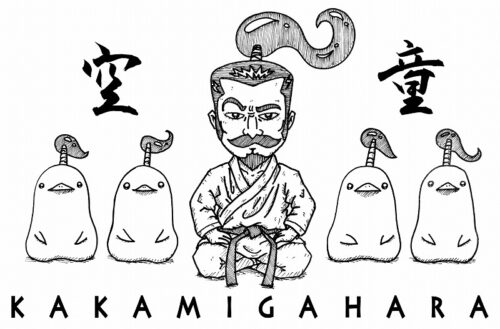みなさん、「床の間には上がっちゃダメ!」って聞いたことありますよね?
「そこは神聖な場所だから」とか、「昔からの決まりだから」とか言われるけど、実際のところどうなの?って思いませんか?
今回は、この「床の間の謎」にズバッと切り込んでいきます。
そもそも床の間ってなんなの?
床の間っていうのは、いわば「家の中の特別なショーケース」みたいなもの。
仏壇みたいに拝む場所でもなく、畳の間のただの角っこでもない。
格式とセンスを見せるための空間なんです。
もともとは武士のステータスシンボルでした。
「俺んち、こんなに立派な掛け軸あるぜ!どうよ?」みたいな感じです。
今でいうと、リビングに高級スピーカーやオシャレな絵を飾って「この家、センスあるでしょ?」ってやるのと一緒。
戦国時代の武士たちが、権威や格式を示すために作ったのが始まりで、それが江戸時代になると、庶民の家にも広まっていったんです。
なぜ床の間に上がっちゃダメって言われるの?
さあ、ここで本題です。
「床の間に上がるな!」って言われる理由は、大きく分けて3つあります。
身分の象徴だったから
昔は、お殿様や偉い人が座る場所だったんです。
だから、一般人がホイホイ上がるのは「おい、それ、畏れ多いぞ!」ってなるわけです。
今でいうと、会社の社長室にズカズカ入って社長の椅子に座るようなもの。
それは、怒られますよね。
そこに神様やご先祖様がいる(ことになっている)
床の間には掛け軸や花が飾られますが、実はこの掛け軸、昔から「神仏の絵」や「教えの書」がよく飾られてたんです。
だから、「ここは神聖な場所」っていう考えが広まったんです。
仏壇みたいなもので、「ご先祖様や神様がいるから失礼のないようにしなさい」ってことですね。
床の間の構造上、上がると危ない
床の間って普通の畳の部屋よりちょっと高く作られてるんです。
だから、上がると段差がある分、踏み外したり、バランスを崩してゴロンと転ぶことも。
もしそこで高価な壺や掛け軸を倒しちゃったら…家主は血の涙を流しますよね。
「床の間に上がると神様が怒るぞ!」じゃなくて、本当の理由は「床の間に上がると家主が怒るぞ!」だったんです(笑)。
でも、絶対に上がっちゃダメなの?
結論から言うと、「絶対にダメ!」ってわけではないんです。
例えば、床の間に仏壇を置いてる家では、ご先祖様に手を合わせるために床の間に座ることもあるし、床の間の掃除をするときには、当然上がることになります。
要するに、「意味を理解して、TPOをわきまえればOK!」ってことですね。
まとめ
1. 床の間は、昔の武士が「オシャレ&格式」を見せるために作った場所
2. 神様やご先祖様を祀る空間とされているので、むやみに上がるのはNG
3. 物理的に段差があるので、壊したり転んだりしないように注意
4. でも絶対に上がっちゃダメなわけじゃない!掃除や仏壇のお参りならOK
つまり、「ただの伝統だから」とか「神聖だから」って理由だけでダメってわけじゃない。
でも、「なんとなくマナーとして守ると常識がある人」って感じですね。
日本の伝統って、知ると面白いし奥が深いですね。