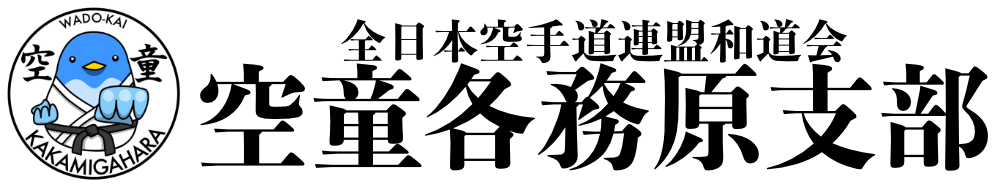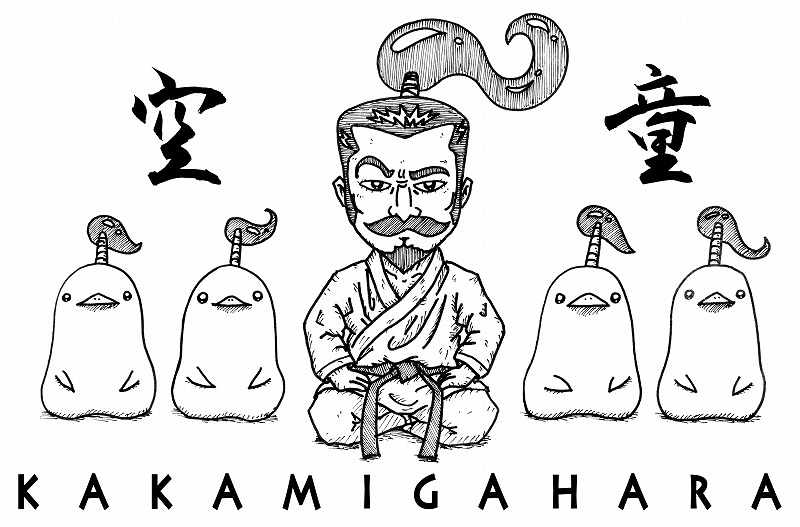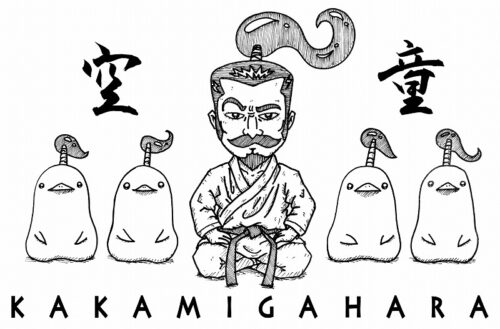忍耐力とは?
忍耐力っていうのは、「辛抱して耐える力」だと思われがちですけど、本当は「自分の気持ちをコントロールする力」なんです。
だから、親が「この子に忍耐力をつけさせよう!」って思って、やたら厳しくしたり、我慢を強要したりすると、逆にうまくいかない。
むしろ、子どもが「この状況をどう乗り越えようかな?」って考える力を育てることが大事なんです。
じゃあ、具体的に親が何をすればいいのか?
① 「楽しさ」と「小さな挑戦」をセットにする
忍耐力って、いきなり大きな試練で鍛えられるものではないんです。
小さなチャレンジをクリアして、「できた!」っていう成功体験を積み重ねることが大事。
例えば、ゲームが好きな子なら「このゲーム、ちょっと難しいけどクリアできるかな?」って挑戦させる。
勉強でも、「10分間だけ集中してやってみよう!」っていう短い時間から始める。
そうすると、脳が「やればできる!」って学習するんですね。
ここで大事なのは、「楽しさ」とセットにすること。
楽しくないと人間は続けられないから。
ゲーム感覚で「やったら面白いことがある!」って思わせると、子どもは自然に挑戦するようになるんですね。
② 「待つ力」を親が見せる
親がせっかちだと、子どもも「すぐ結果を求める」ようになってしまう。
だから、親がまず「待つ力」を見せることが大事。
例えば、子どもが靴を履くのに時間がかかっても、「早くしなさい!」って言わずに、黙って見守る。
宿題をしてるときも、「ちゃんとやってる?」ってすぐ確認せずに、終わるまで待ってみる。
そうすると、子どもは「じっくり取り組むことって大事なんだな」って感じるようになる。
だって、親が「焦らない姿」を見せてるんだから、子どもも自然とそうなりますよね。
③ 失敗を責めずに「気づかせる」
忍耐力がある子って、「失敗しても立ち直れる子」なんです。
だから、子どもが失敗したときに、「なんでできないの!」って責めると、チャレンジする気持ちがなくなってしまう。
むしろ、「どうしたら次はうまくいくと思う?」って問いかけて、考えさせることが大事。
例えば、子どもが工作を作ってて、うまくいかなくてイライラしてたら、「そういうとき、どうしたらいいかな?」って聞いてみる。
すると、最初は「わかんない!」って言うかもしれませんけど、「ちょっと休憩してからやる?」「別の方法を考えてみる?」ってヒントを出してあげると、だんだん「乗り越える力」がついてくる。
こういうのを繰り返してると、子どもは「どんなことも工夫すればなんとかなる」って思えるようになるんですね。
忍耐力って、ただ「我慢させること」じゃなくて、「自分で乗り越える力」を育てることなんです。
まとめ
親ができることは、
✅「小さな成功体験を積ませる」
✅「親が待つ力を見せる」
✅「失敗しても考えさせる」
の3つ。
この3つをやってたら、子どもは自然と「どんなことも乗り越えられる力」を身につけていくようです。
大事なのは、「楽しく、ゆっくり、気づかせる」こと。
子どもに忍耐力をつけさせたいなら、まずは親が「楽しんで待つこと」から始めてみようではありませんか!