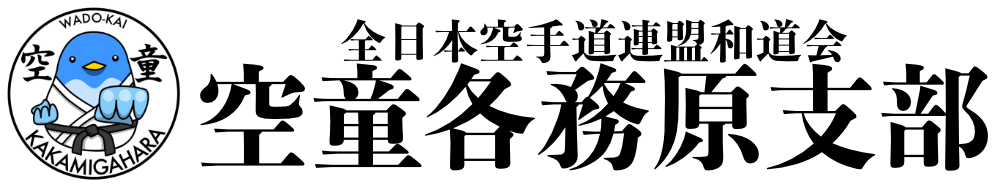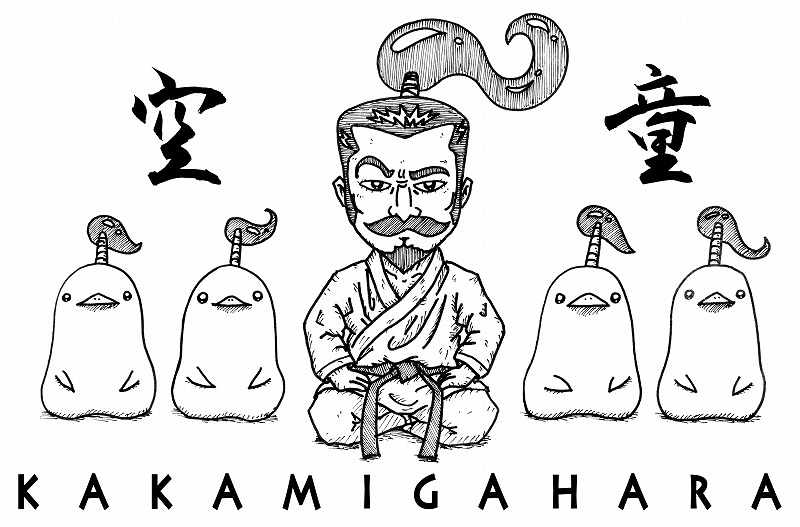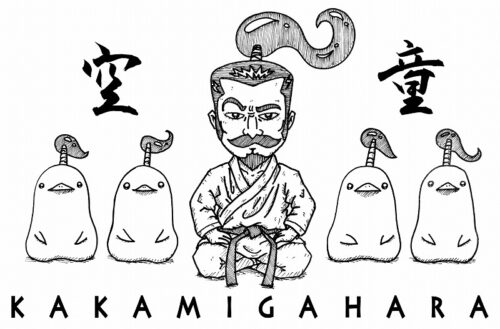道場の正面に神棚!?なんで?
昔ながらの道場に入ると 正面の一番いい場所 に、今はないところが多いけど 神棚 がありますよね?
で、先生が「正面に礼!」って言うから、みんなで ペコッ!ってするわけです。
でも、最初の頃は「え、道場の壁に向かって礼??」って思う人もいるんです。
いやいや、それ ただの壁じゃないんです。
そこに神様がいらっしゃる!ってことになってるんです。
「え、神様って道場にいるの?」
そうなんです!でも、別に「怒って厳しくする神様!」みたいなのがいるわけじゃないんです(笑)。
武道の道場に神棚があるのには、ちゃんとした意味と歴史があるんです。
【昔の日本人は、なんでも神様にする】
日本って国は、昔から「どんなものにも神様が宿る」って考える文化なんですね。
八百万の神(やおよろずのかみ) ともいいますけど。
山にも、川にも、木にも、食べ物にも、ぜ〜んぶ神様がいる。
たとえば、お米にも 「お米の神様」 がいるし、
剣道の竹刀にも 「武道の神様」 が宿るって思われてたんですね。
だから当然、「道場にも神様が必要だ!」 ってことになったんです。
だって、道場っていうのは、ただの建物じゃなくて 「心と技を磨く神聖な場所」 ですからね。
昔の武士たちは、道場を神聖な場所にした!
武道の歴史をさかのぼると、昔の 武士たち は剣術や柔術を学ぶ 道場 を持っていたんです。
でも、そこは 「ただの練習場」 じゃない。
武士にとって 「剣を振るうこと」=「命がけ」 なわけです!
だから、戦いの前には 「神様、今日もよろしくお願いします!」 ってお願いしてました。
で、剣術道場の先生たちは考えたんです。
「よし!道場の正面に神様を祀ろう!」
「そうすれば、ここがもっと神聖な場所になる!」
こうして 道場の正面に神棚を作る っていう文化が生まれたんですね。
【神棚の中には何がある?】
道場の神棚には 「御札(おふだ)」 が置いてあることが多いんです。
よくあるのは、
😊 「天照大神(あまてらすおおみかみ)」 → 日本の最高神。
😊 「鹿島神宮の武道の神様」 → 武士の守り神。
😊 「道場の開祖の写真」 → 創始者をリスペクト。
これがあることで、道場の先生たちはこう思うわけです。
😊 「神様が見てるから、ちゃんと稽古しよう!」
😊 「みんながケガしないように、道場を守ってください!」
😊 「この道場がもっと発展しますように!」
要するに 「武道の神様が見守ってるよ!」 っていう空気を作るために、
神棚が どーん! と道場の正面にあるわけなんです。
「神棚があると、道場の空気が変わる!」
さてさて、みんな考えてみてください。
もし道場に 神棚がなくて、ただの壁 だったら、どんな気分になりますか?
😧「ただの建物・・・」
😧 「稽古しに来たっていうより、体育館みたい・・・」
😧 「なんか・・・ありがたみがない・・・?」
でも、正面に神棚や創始者の写真とかが バッチリ! あると、
😊 「おぉ、ここは ‘武道の聖地’ って感じがする!」
😊 「神様(創始者)に見られてると思うと、真剣になる!」
😊 「道場が ‘特別な場所’ に感じる!」
ってなるわけなんです。
要するに 「神棚や創始者の写真があることで、道場の雰囲気がピリッと締まる!」 ってことなんですね。
まとめ
😊 「道場に神棚があるのは、道場を神聖な場所にするため!」
😊 「武士たちが ‘武道は神様とともにある’ って考えたから!」
😊 「神様が見てるから、ちゃんと稽古しよう!って気持ちになる!」
😊 「神棚があることで、道場の雰囲気がピシッと引き締まる!」
道場の神棚っていうのは 「ただの飾り」 じゃなくて、
「武道の心を大切にするためのシンボル」 なんです!
だから、これから道場で 「正面に礼!」 するときは、
😊 「今日もよろしくお願いします!」
😊 「道場のご先祖様、ありがとうございます!」
😊 「神様、オレをもっと強くしてください!」
っていう 感謝の気持ち を込めてみましょう!
そしたら、不思議と技が冴えてきますから!