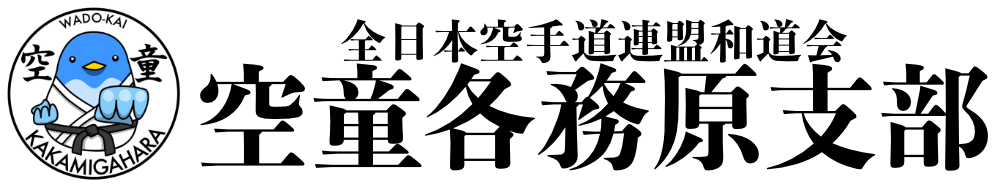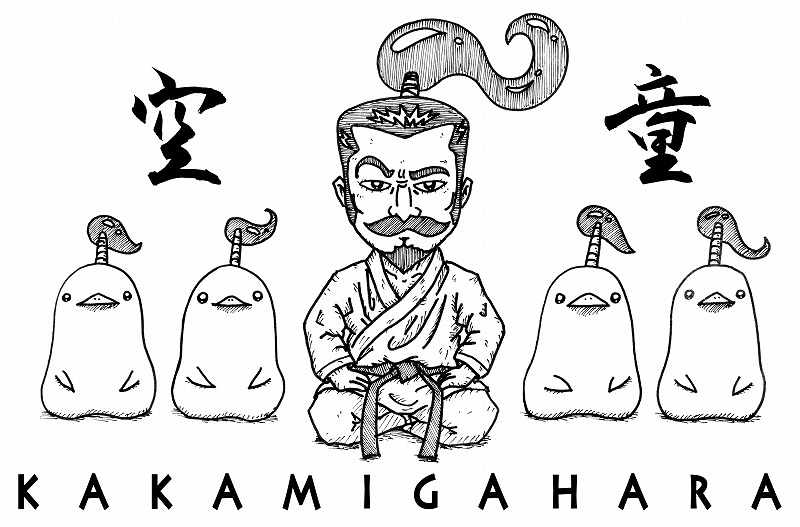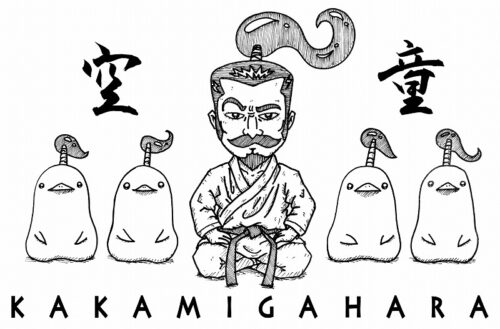空手を習うと集中力が上がるって言われますけど、「なんで?」って聞かれると、ちゃんと説明できる人は意外と少ないと思います。
今回は、それをわかりやすく、面白く説明していきます!
「気を抜いたら痛い目に遭う」法則
まず、人間って「ヤバい!」と思ったときに一番集中するんです。
たとえば、道を歩いてて急に自転車が猛スピードで向かってきたらどうします?
ボーッとしてる人でも一瞬で「やべっ!」ってなって、サッと避けますよね?
空手も同じ。
試合でも形の稽古でも、「気を抜いたら負ける」「気を抜いたら突かれる」っていう状況だから、自然と集中するようになるんです。
ゲームで言うと、常にHP1でボス戦やってるみたいなもんです(笑)。
一瞬でも油断したらやられるから、脳が勝手に集中モードに入る。
この「集中モード」を何度も繰り返すことで、普段の生活でも自然に集中できるようになるんですね。
「一瞬で判断する」トレーニング
空手の試合や組手って、一瞬の判断で動かないといけません。
「相手の蹴りがくる!」
「今なら反撃できる!」
こういう判断を毎回、瞬時にしなきゃいけない。
これって、いわば「脳の筋トレ」なんです。
普段の生活でも、「今やるべきことは何か?」を瞬時に判断できるようになります。
結果、「気が散る前にやるべきことをやる」っていう集中力が身につくんです。
たとえば、テスト勉強や仕事でも「今やる!すぐやる!」ってスイッチが入るようになる。
「あとでやろう~」とか「なんかスマホ触っちゃうな~」みたいなのが減るんです。
「形は究極の集中力トレーニング」
空手には「形」っていう、一人で決まった動きをする練習があります。
でね、形って「ただ動けばいい」わけじゃなくて、手の角度、足の向き、呼吸、目線…
全部意識しなきゃいけない。
この「複数のことを同時に意識する」って、めちゃくちゃ脳を使うんです。
しかも、やればやるほど精度が上がっていく。
だから、形をしっかり練習している人は、他のことでも集中しやすくなるんです。
たとえば、勉強するときも「一つのことに集中する力」が鍛えられてるから、
周りがうるさくても「今はこれに集中!」ってスッと切り替えられるようになるんですね。
「礼儀=集中力の訓練」
空手では「礼に始まり礼に終わる」って言いますよね。
道場に入るときは「お願いします!」と元気よく挨拶するし、
稽古中も「先生の話を聞くときは姿勢を正す」「相手の目を見て話す」など、
礼儀作法がすごく大事にされます。
これって、全部「意識を向ける練習」なんです。
だらしない姿勢でボーッとしてると、先生にすぐ注意されます。
でも、これを繰り返してると、日常生活でも「今この瞬間に意識を向ける」っていう習慣がつく。
これがそのまま集中力につながるんです。
「心を無にする=究極の集中」
空手ってただのスポーツじゃなくて、「武道」なんです。
で、武道っていうのは、心を整える修行でもあるんです。
よく「無心で戦え!」って言いますよね。
これは「何も考えない」って意味じゃなくて、雑念をなくして「目の前のことだけに集中する」ってこと。
この「無心の境地」を目指して稽古をしていくと、日常生活でも余計なことを考えずに「今やるべきこと」に集中できるようになる。
勉強でも、仕事でも、人の話を聞くときでも、スッと集中できる。
これが、空手を習うことで得られる「究極の集中力」なんですね。
まとめ
1. 「気を抜いたら痛い目に遭う」から、自然と集中する。
2. 「一瞬で判断する」ことで、脳が鍛えられる。
3. 「型の練習」で、一つのことに意識を向ける力がつく。
4. 「礼儀作法」が、集中する習慣を作る。
5. 「無心」を目指すことで、余計なことを考えずに集中できるようになる。
こうやって考えると、空手って「最強の集中力トレーニング」ですね!
空手を続けていると、勉強も仕事も、何をやるにも「スッと集中できる人」になれますよ。