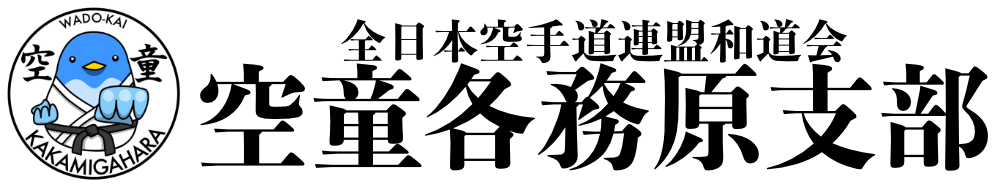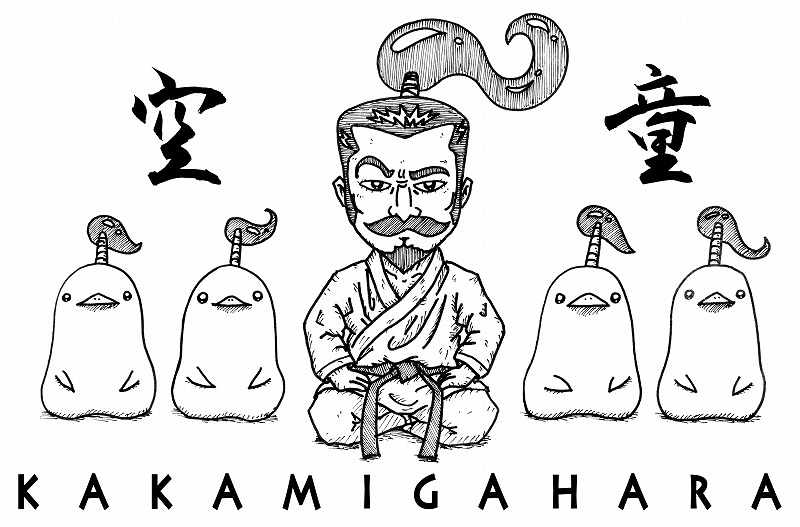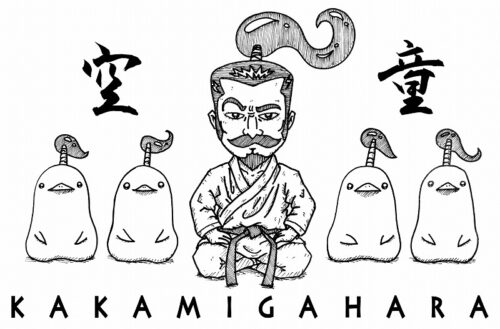空手の形っていうのはですね、昔の武術家たちが
「もし敵に囲まれたらどうする?」
「もし武器を持ったヤバい奴が来たら?」
って考えて、
「よし、こうやって倒そう!」って作った動きの集大成なんです。
たとえば「ピンアン(平安)」って形があるんですけど、これは昔の偉い先生が
「この形を覚えたら安心して夜道を歩けるぞ!」
ってことで「平安」って名前をつけたらしいんです。
今の時代に夜道で空手の形をやってる人はいなませんけど(笑)。
形の歴史ってどうなってるの?
空手ってもともとは沖縄発祥なんですけど、昔の沖縄の人たちは
「武器を持っちゃダメ!」
っていうお触れが出てたんです。
「いやいや、そんなの無理でしょ!だって、もしヤバい奴が来たらどうすんの?」
ってことで、
「じゃあ素手で戦う方法を極めよう!」
ってなったんですね。
それで、中国や日本の武術と混ざり合いながら、「形」ができていったんです。
たとえば「ナイファンチン」って形は、中国拳法の影響を受けてるし、
「バッサイ」は「敵の陣地に突っ込めー!」みたいな意味があるんです。
昔の人は「この形を極めたら最強だ!」って信じてたんですね。
形をやる意味ってあるの?
「いやいや、こんなの昔の戦い方でしょ?今の時代に必要?」
って思うかもしれませんけど、これが大アリなんです!
形をやると、「体の使い方」 がめちゃくちゃ上手くなる。
力の入れ方、抜き方、バランスの取り方、全部形に詰まってるんです。
だから、「形を極めた人は強い!」って言われるわけです。
それに、形ってめっちゃカッコいいんです。
試しに公園で「ウンスー(雲手)」とかやったら、
周りの人が「えっ、なんか武術の達人いる!?」ってなりますから(笑)。
まとめ
😊 形は「昔の戦いの知恵」が詰まった武道の集大成!
😊 沖縄の武術家たちが考えた「究極の戦い方」!
😊 現代でも役に立つし、何よりカッコいい!