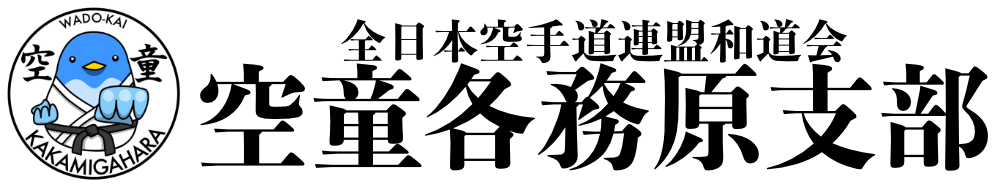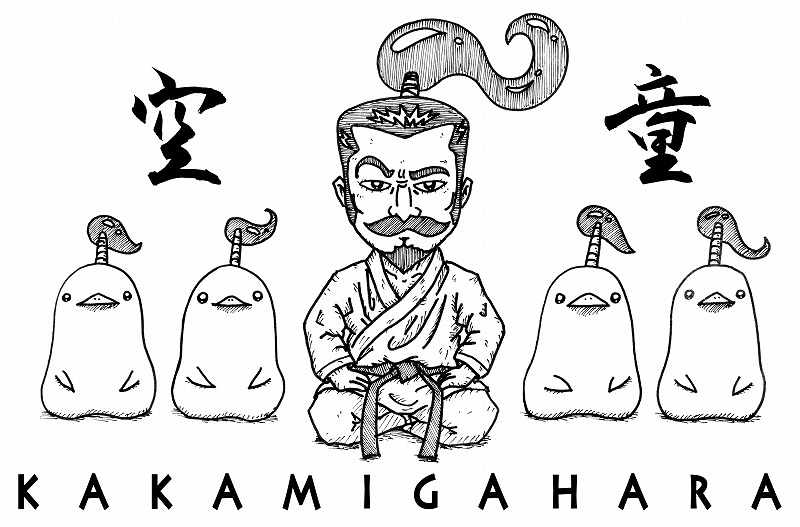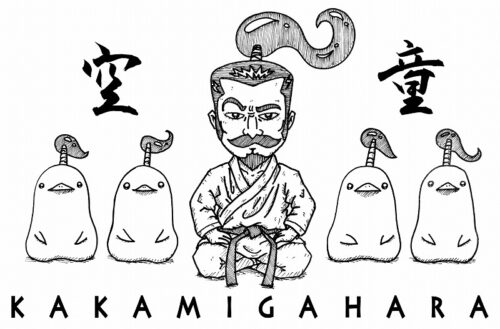和道流ってどんな空手?
みなさんは「和道流(わどうりゅう)」と聞いて、どんなイメージがありますか?
ちょっとやさしい響きがあるな、とか、沖縄発祥の空手とは少し違うのかな、とか思ったりするかもしれませんね。
そのイメージ、じつは半分正解です。
和道流は日本で生まれた四大流派の一つで、沖縄空手に日本の伝統的な武術(特に柔術や剣術)の動きをたっぷり取り入れている流派です。
その「和」という字には、日本らしい「和を尊ぶ心」、そして相手に対する「和らぎ」や「調和」という深い意味が込められています。
単に力比べをするだけじゃなく、自分と相手が心地よく向き合えるような動き、それが和道流の魅力です。
創始者・大塚博紀先生ってどんな人?
和道流をつくったのは、大塚博紀(おおつか ひろのり)先生です。
1892年(明治25年)、岩手に生まれた大塚先生は、とにかく幼いころから武術が大好きな少年だったそうです。
6歳のころから地元で盛んな神道揚心流(しんとうようしんりゅう)という柔術を学び、若いころには師範代に選ばれるほどに成長しました。
神道揚心流は、相手に対して無理に力をぶつけるのではなく、体さばきで相手をかわし、バランスを崩させることに長けた流派です。
そのエッセンスは、後に和道流に大きな影響を与えています。
その後、東京へ出た大塚先生は、当時日本に沖縄から空手を広めていた船越義珍(ふなこしぎちん)先生に出会い、本格的に空手を学び始めます。
そして空手に魅了されつつも、さらに「日本らしい動き」「柔らかい受け方」を取り入れるべきではないかと考えはじめるんです。
船越義珍との出会いと空手に対する視点の違い
船越義珍先生の空手は沖縄伝来のもので、どちらかというと力強い突きや蹴りが主体です。
それに対して、大塚先生はもともと柔術出身。
相手に力いっぱいぶつかるだけではなく、相手が突いてきたらそれを受け流し、するりと入身(いりみ)するような動きが体に染みついていました。
あるとき稽古中に、船越先生が大塚先生に突きを出したことがあったそうです。
そのとき大塚先生はその突きをかわしざまに崩し、自然に相手を投げるような動きを見せたといいます。
この一瞬に、空手に柔術が溶け込んだ新しい可能性が見えた、と大塚先生は後に語っています。
和道流誕生のきっかけ — 柔術と空手の融合
「ただ真っ向から突き合ってもいいけど、それだけじゃないはずだ」
そう考えた大塚先生は、自分なりに動きやすく、かつ日本人にとって自然な動きを空手に取り入れていきました。
そのひとつが、**体捌き(たいさばき)**です。
体さばきとは、相手の突きや蹴りに対して真正面から受けるのではなく、体をスッと横にさばき、相手の力が空を切る間に反撃に出る動き。
このテクニックは神道揚心流から学んだエッセンスでした。
さらに、居合や剣術で養った間合い(ま あい)の感覚も取り入れられていきます。
1934年には、自ら道場を開き、これが和道流空手の出発点となりました。
そして1938年に流派名を「和道流」と正式に定めたのです。
「和」の精神はそのまま、争わず和する、無駄な力を使わない、そんな思いを込めて名付けられました。
大塚先生の名言
大塚先生は、和道流の哲学をとても大切にしていて、弟子たちにこんな言葉を残しています。
「空手とは人と争うものにあらず、人と和するものなり。」
この一言には和道流の神髄が詰まっています。
相手とぶつかり合うだけでなく、気配を読み、自分を整え、相手に対して柔らかく動き、その場を丸く収める。
そのために心身を鍛えるのが和道流なんですね。
また、
「相手に逆らわぬこと、それこそが勝つ秘訣だ」
という名言もあります。
これは、まさに柔術と空手が融合した和道流の根本哲学です。
自分から力を使い果たさず、相手に流れを任せることで、逆にその力を利用する。
その感覚を体得するには長い稽古が必要ですが、一度つかめば一生使えます。
戦後から現代へ — 和道流が世界に広まった理由
第二次世界大戦が終わると、日本は混乱期に入り、一時期空手や武術の稽古は停滞しました。
それでも大塚先生は再び活動を再開し、弟子たちに和道流を広めていきます。
和道流が海外へ広がったきっかけとなったのは、1952年にイギリスからやってきた空手愛好家たちとの交流です。
とくにイギリスの空手界に影響を与えたのが大塚先生の弟子たちです。
その後、和道流はヨーロッパ各地に広がり、1970年代にはイギリスに和道流の道場が数十か所できるほどに人気となりました。
さらに、ヨーロッパで和道流が人気となった理由には、
- 体格に頼らない動き
- 女性や子どもも稽古しやすい体さばき
- 柔術由来の応用が実践的に見えたこと
- 日本人らしい「和」の哲学が珍しく新鮮だったこと
などがあります。これらが外国人にとっても新しく魅力的に映ったのです。
世界大会と和道流の広がり
1980年代からは、和道流出身の選手たちが全日本空手道選手権大会や世界空手道選手権大会に出場し、頭角を現していきます。
そしてイギリス、イタリア、フランス、アメリカ、カナダ…と世界中に広がっていきました。
和道流は、日本に根付いた伝統武術でありながら、現代競技としての洗練も進めてきた流派です。
そのため、試合では「相手をかわして出る」「相手に反応させて逆を取る」という動きが生きることから、見ていて美しく、かつ実践的な試合が展開されます。
このスタイルが現代空手界に一石を投じ、ますます和道流に興味を持つ人が増えていきました。
大塚先生から次世代へ、さらに未来へ
大塚博紀先生は1982年に惜しまれつつも亡くなりましたが、その志と教えは二代目宗家の大塚博紀(同名ですが二代目)に受け継がれ、さらにその弟子たちによって脈々と今に伝わっています。
今では和道流は日本国内だけでなく、世界中に数万人規模の修行者がいて、国際大会やセミナーには数百人単位で集まるほどです。
その中には試合を目標にする選手もいれば、健康増進や護身術、精神修養を目的とする人もたくさんいます。
和道流のこれから
これからも和道流はその哲学と技術を大切にしながら、時代に合わせて進化していくでしょう。
「和」の精神に基づき、どんな相手と出会っても争わずに柔らかく対応できる心と体、それこそが和道流の真髄です。
その思いに触れると、ただ強くなりたいだけではなく、相手との調和を大切にする生き方そのものに憧れる人が増えていきます。
そしてその輪が、国や文化を超えてさらに広がり続けることでしょう。
まとめ
和道流はただの武術ではありません。
「調和すること」「相手を理解すること」「争いを超えて自分を磨くこと」、そんな深い哲学を体と心で学べる、奥行きのある流派です。
大塚博紀先生が残した名言「相手に逆らわぬこと、それこそが勝つ秘訣だ」は、きっとこれからの時代を生きる私たちにとっても大きなヒントになりますね。